レトロゲームといえば、名作ソフトの数々を思い出す方も多いでしょう。ですが、それらのソフトは“ハードウェア”という舞台があってこそ成立していました。
今回は1980年代から平成初期にかけて登場した家庭用ゲーム機を時系列順に紹介しながら、ゲームの進化を振り返っていきます。
1983年
ファミリーコンピュータ(7月15日)

Evan-Amos – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
任天堂が放った家庭用ゲームの革命児。
“ファミコン”の愛称で親しまれ、家庭にゲーム文化を根付かせました。『マリオ』『ゼルダ』『ドラクエ』など、国民的タイトルがここから誕生します。
SG-1000(7月15日)

Evan-Amos – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
セガ初の家庭用ゲーム機。ファミコンと同日発売。
性能やゲーム内容の面でファミコンに一歩及ばず、ややマイナーな存在に。Z80 CPUを採用し、アーケード移植を中心に展開。
1984年
SG-1000 II(7月31日)

https://segaretro.org/User:Black_Squirrel – https://segaretro.org/SG-1000_II, CC0, リンクによる
SG-1000の改良版。デザイン刷新とコントローラーの着脱機能追加。ソフトは互換性ありで、SG時代の締めくくり。
1985年
セガ・マークIII(10月20日)

Muband – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
SGシリーズの後継で、セガが本気を出したファミコン対抗機。色数や解像度でファミコンを凌駕し、アーケード移植に強みを持つ。
1986年
ファミコン ディスクシステム(2月21日)

Evan-Amos – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
任天堂がファミコンの拡張として投入した周辺機器。ディスクメディアによりセーブ機能と低コスト化を実現。『ゼルダ』『メトロイド』『悪魔城ドラキュラ』などの名作がここから生まれました。
1987年
FM音源ユニット(セガマークIII用)
セガマークIIIに装着することで、FM音源による高音質なBGM再生が可能に。アーケードの雰囲気を自宅でも楽しめるように。
セガ・マスターシステム(10月)

Evan-Amos – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
マークIIIの上位互換モデルで、FM音源を標準搭載。主に海外市場で展開され、特に欧州・南米でヒット。
PCエンジン(10月30日)

Evan-Amos – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
NECとハドソンの連携で誕生した高性能マシン。8bit機ながら16bit級の描画能力を持ち、グラフィックの綺麗さに驚いたユーザーも多数。『R-TYPE』『桃太郎伝説』『カトケン』などが人気に。
1988年
メガドライブ(10月29日)

Evan-Amos – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
セガが放つ本格16bitマシン。アーケード移植、スピード感、硬派なイメージでゲーマーを魅了。『ソニック』『ゴールデンアックス』『シャイニング・フォース』などの名作が登場。
CD-ROM²(12月4日)

Jzh2074John Cummingshttps://en.wikipedia.org/wiki/ja:User:VICHotaru3 – File:NEC_PC-Engine_(1987)_1.jpgFile:OnLive_controller.jpgFile:OnLive_MicroConsole_TV_Adapter_end_1.jpgFile:PC_Engine_Duo-RX.jpgFile:V.Flash_Console.jpg, CC 表示 4.0, リンクによる
PCエンジンの周辺機器として登場。世界初のCD-ROMゲームシステムで、音声演出・音楽品質が飛躍的に向上。『天外魔境』『イースI・II』『ときメモ』など。
1990年
スーパーファミコン(11月21日)

Evan-Amos – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
ファミコンの後継機として、任天堂が投入した16bitマシン。回転・拡大縮小などの特殊効果や高音質音源が特徴。『FF6』『クロノ・トリガー』『マリオRPG』など、不朽の名作を多数輩出。
1991年
メガCD(12月12日)

軍事用懐中電灯 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる
メガドライブ用CD-ROM拡張機。アニメ、実写、フルボイスなど表現力が飛躍。『ルナ』『シルフィード』『うる星やつら』などが代表格。
1993年
メガドライブ2(4月23日)
メガドライブの小型・軽量モデル。AV端子が標準装備され、コストダウンを実現。デザインも刷新。
メガCD2(4月23日)

Evan-Amos – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
メガCDの後継機。メガドライブ2との接続を前提に小型化され、操作性や拡張性が改善された。
ハード発売年まとめ
| 年 | ハード名 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1983 | ファミリーコンピュータ | 7月15日 | 家庭用ゲームの原点 |
| 1983 | SG-1000 | 7月15日 | セガ初の家庭用ゲーム機 |
| 1984 | SG-1000 II | 7月31日 | SG-1000の改良版 |
| 1985 | セガ・マークIII | 10月20日 | SGシリーズの正統進化 |
| 1986 | ファミコン ディスクシステム | 2月21日 | 書き換え可能な新メディア |
| 1987 | FM音源ユニット | – | マークIII用音源拡張 |
| 1987 | セガ・マスターシステム | 10月 | FM音源内蔵の海外モデル |
| 1987 | PCエンジン | 10月30日 | NEC×ハドソンの高性能機 |
| 1988 | メガドライブ | 10月29日 | セガの16bit本命 |
| 1988 | CD-ROM2 | 12月4日 | 世界初CD-ROMゲーム機 |
| 1990 | スーパーファミコン | 11月21日 | 任天堂の16bit王者機 |
| 1991 | メガCD | 12月12日 | メガドライブ用CD拡張 |
| 1993 | メガドライブ2 | 4月23日 | 小型・廉価モデル |
| 1993 | メガCD2 | 4月23日 | メガCDの後継機 |
まとめ
ゲームの進化とは、常に“ハードの進化”とセットでした。容量、グラフィック、音、拡張性──制限の中でどれだけ工夫できるかを競い合った時代。
今も色褪せないレトロゲームの魅力は、その時代のハードウェアに刻まれています。懐かしい人にも、これから触れる人にも、「あの頃の空気」を感じてもらえたら嬉しいです。



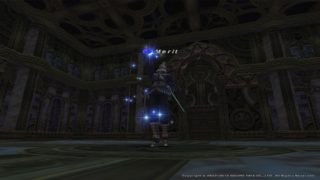






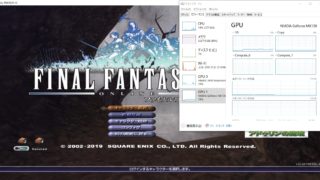



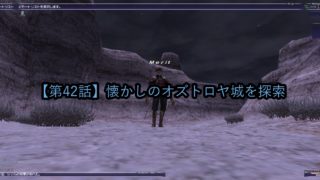


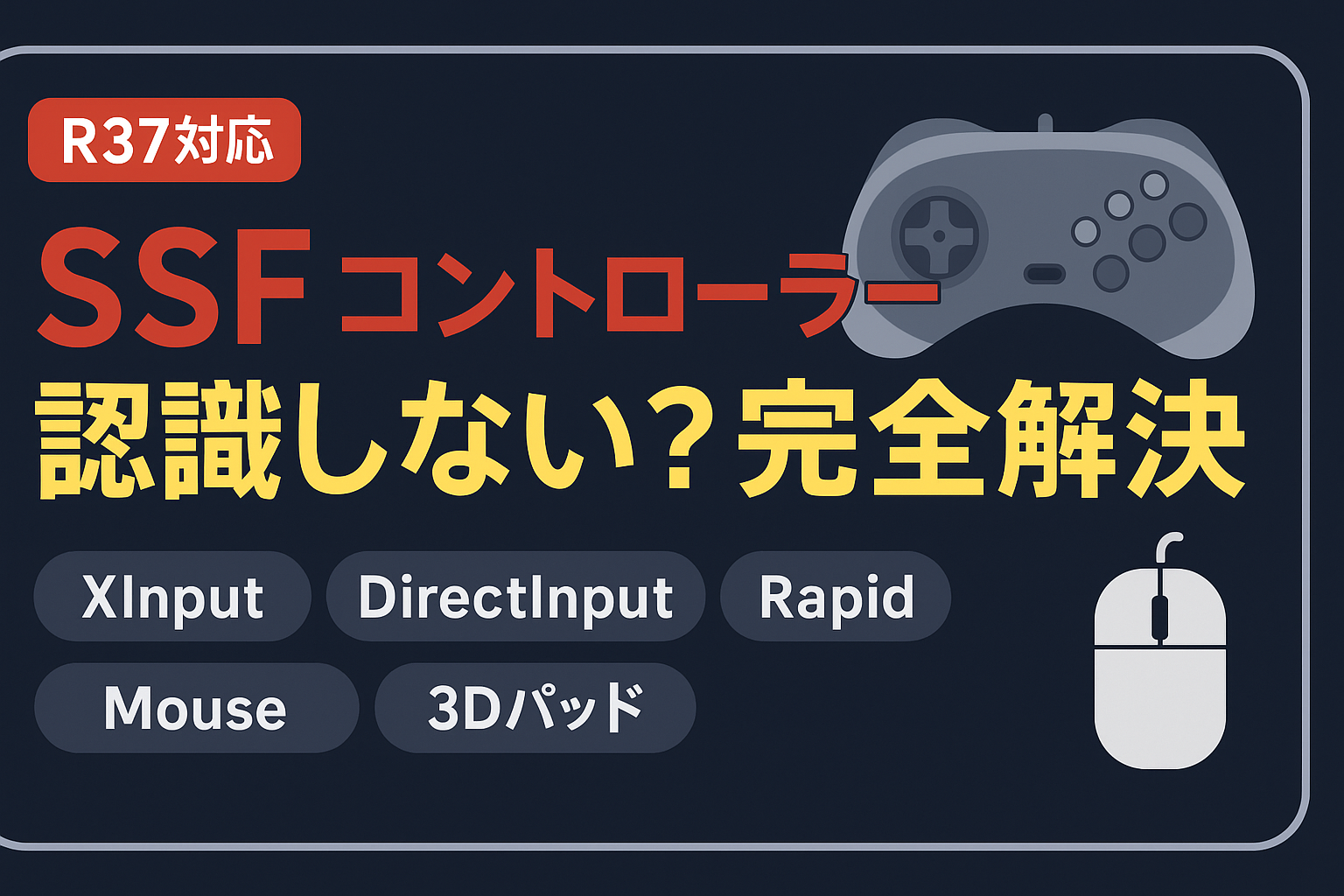


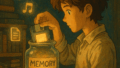
コメント